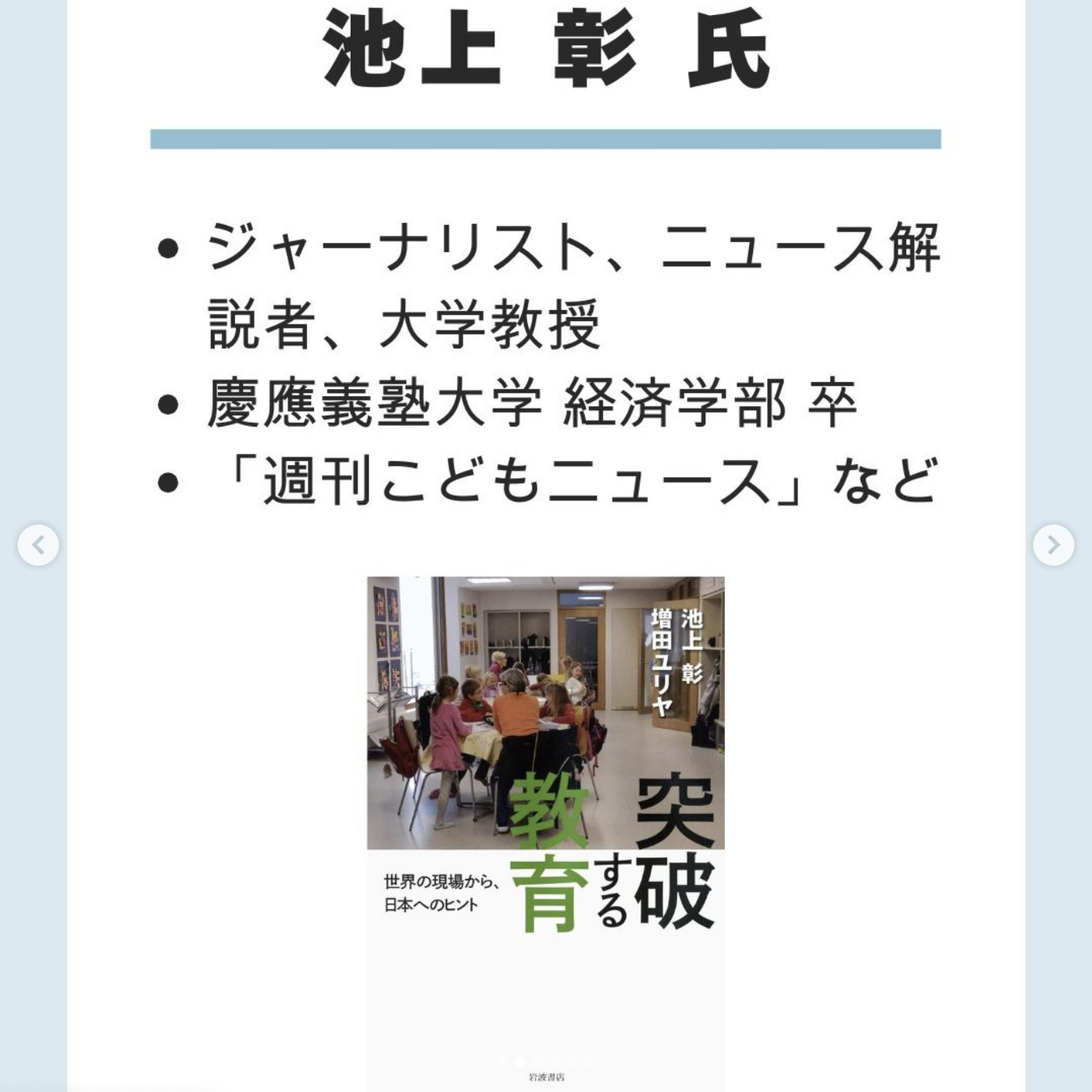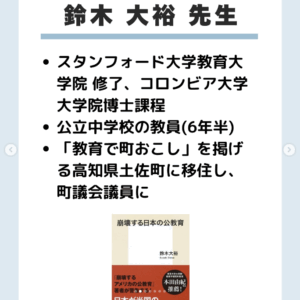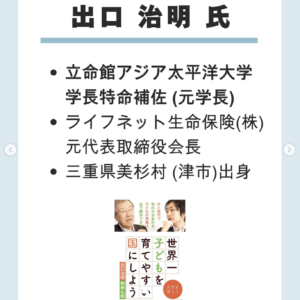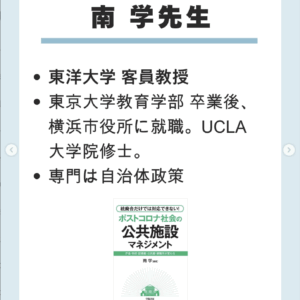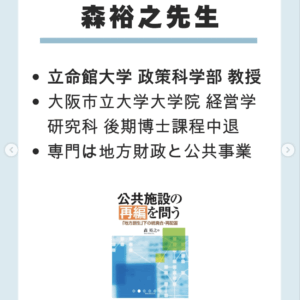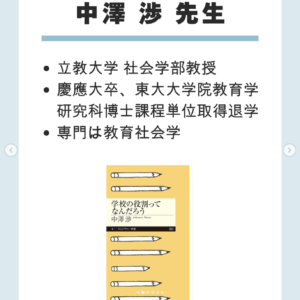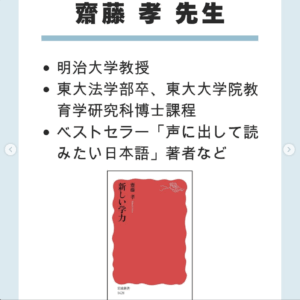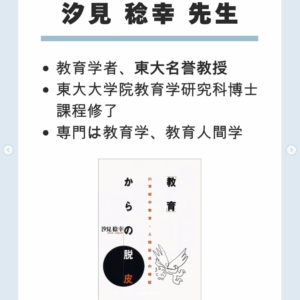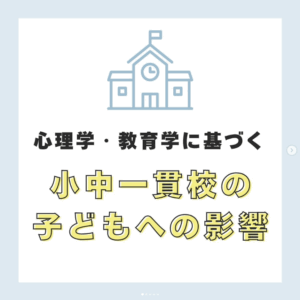目次
小学校の校舎の設計に、子どもも参加する!?
政治や行政に対する、国民/市民の「信頼」が高い、と言われているフィンランド。
(だからこそ、高福祉・高負担が成り立つ)
そんなフィンランドの「信頼」の原点は
教育にあると言います。
例えば、小学校の校舎の設計に、教師だけでなく生徒も参加します。
そして、生徒の声が、実際に反映されているのです。
| 教師 | 生徒 |
|---|---|
| ・教室のつくり、環境にやさしい部材や電力 ・子どもとっての居心地の良さ など | ・どんな教室がいいか? ・学校には何があったらいいと思うか? ↓ ・教室の中に暖かなオンレジ色のソファ ・廊下の途中に、隠れ家のような小さな空間 |
「自分たちも学校づくりに参加しているんだ、
意見を言うと採用してもらえるんだ、
と子どもが実感することに意義があるんです」
(フィンランドの先生の言葉)
居心地のいい場所であることが大切
学校は、子どもたちにとって居心地の良い場所であることが大切です。
- 居心地がいい環境だから人は心を開ける
- 子どもが安心して話せる環境をつくる
- イジメによる自殺を防ぐことにもつながる
信頼の国、フィンランドの特徴
自国の問題を、国民が自分ごととして捉え、政府も国民もお互いの「信頼」をもとに、「合意」の上で、「責任」を持って問題解決に取り組む。
高い「透明性」と「責任感」があるからこそ、強い「信頼」関係が生まれる。
そんな当たり前のことが、
なぜ日本では難しいのでしょうか?
いじめによる自殺事件などが発生するたびに
真相を隠蔽して、ひたすら責任逃れに走る
日本の学校や教育委員会。。。
子どもの声、市民の声を十分聞かずに
ハコモノ作りありきで計画を進めようとしている
某教育委員会。。。
もう一度、下記の条約・法律・条例を、目に焼き付けて頂けないでしょうか?
参照:
https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku_suishin/230323/kihon.pdf
https://www.city.kuwana.lg.jp/kodomo/kodomonokenrijourei.html