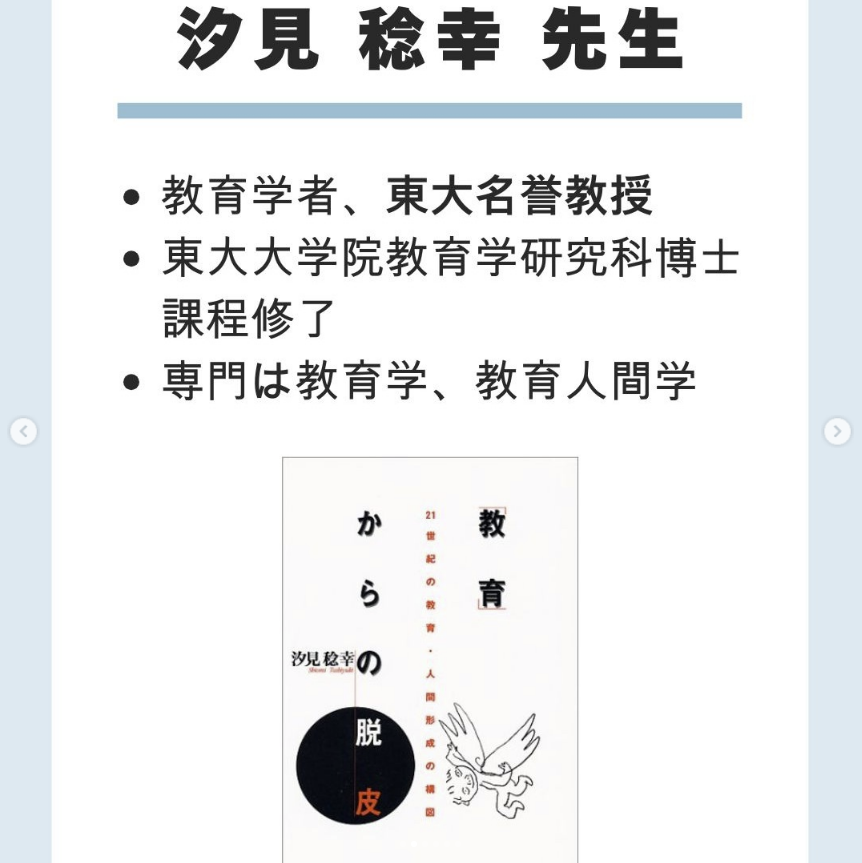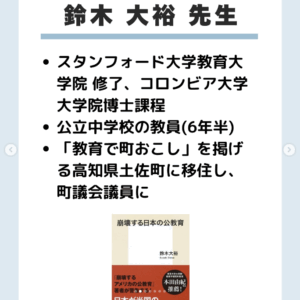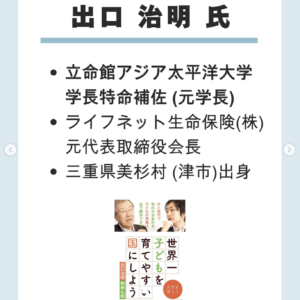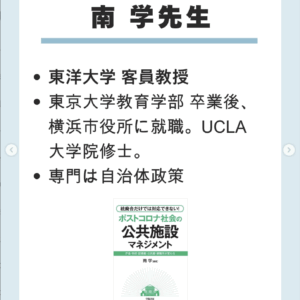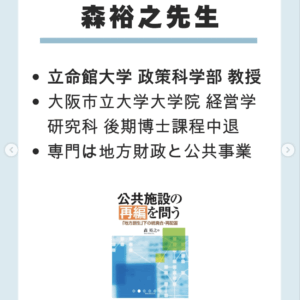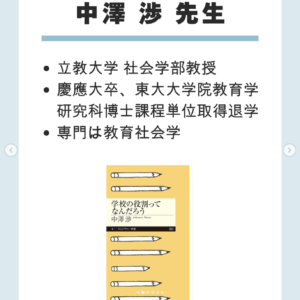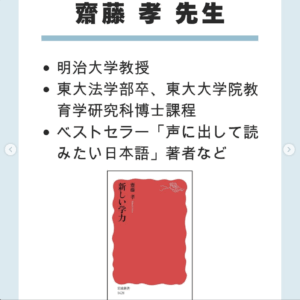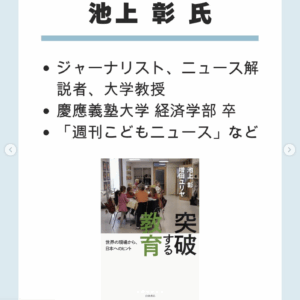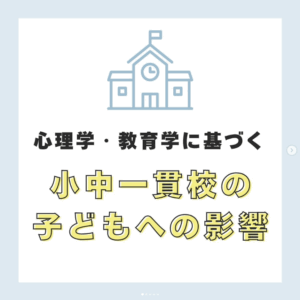子どもたちのために、日本や地域のために
どんな学校/教育にしていくのが良いのか?
そのヒントを、専門家の方々の書籍から、紹介していきたいと思います。
まずは、東大名誉教授の汐見先生の本から。
目次
地域と学校の関係
- 学校こそ地域の中の文化拠点であり、集いの場
- 学校が地域の人間関係をつくる
- 廃校化=地域の廃墟化のシグナル
学校が人々をうまく繋げる場にならないといけない時代
→広大な学区の義務教育学校は、その役割を担えるでしょうか?
むしろ先行例では、地域との関係性が希薄になってしまった、という報告が出ています。
日本の教育の問題点
- 自己肯定感の育成
- 自分で自分の人生を選択する能力の育成
- 答えが1つではない問題を自分で考え、解をつくる力の育成
- 人間形成の役割を学校に過剰に求める
- 情報に操作されず、自分で管理する力の育成
自己肯定感
ありのままの自分を受容し、「自分は自分」と肯定できる。
自己肯定感が低いと…
- 自分を責め、追い詰めやすい
- 他人の目を気にしすぎて、周りに合わせないと不安
- 自己主張できない
- 異文化/異なるものへの許容力が育ちにくい
人間形成
冒険心、挑戦心、集団行動力、社会性、身体能力、忍耐力など。
- 過去の日本:地域で子ども同士の遊びを通じて育まれていた
- 現在の日本:学校に求める教育の1つとして過剰に期待されている
人間形成の問題は、不登校や引きこもりの遠因。
子どもの教育に求められているもの
1.自己肯定感を育む
→大規模な義務教育学校の場合、常に自分より上の子ども、自分よりできる子どもが存在することで、自己肯定感や自信を育みにくい、という大規模調査の結果がありました。
2.社会性などの人間形成
→バス通学や登下校時間の長時間化、放課後に遊べる場所の喪失などは、人間形成にどう影響を及ぼすのでしょうか?
友だちと遊ぶ時間を奪われ、子どもたちが社会性を身につける機会を失ってしまうのではないでしょうか。