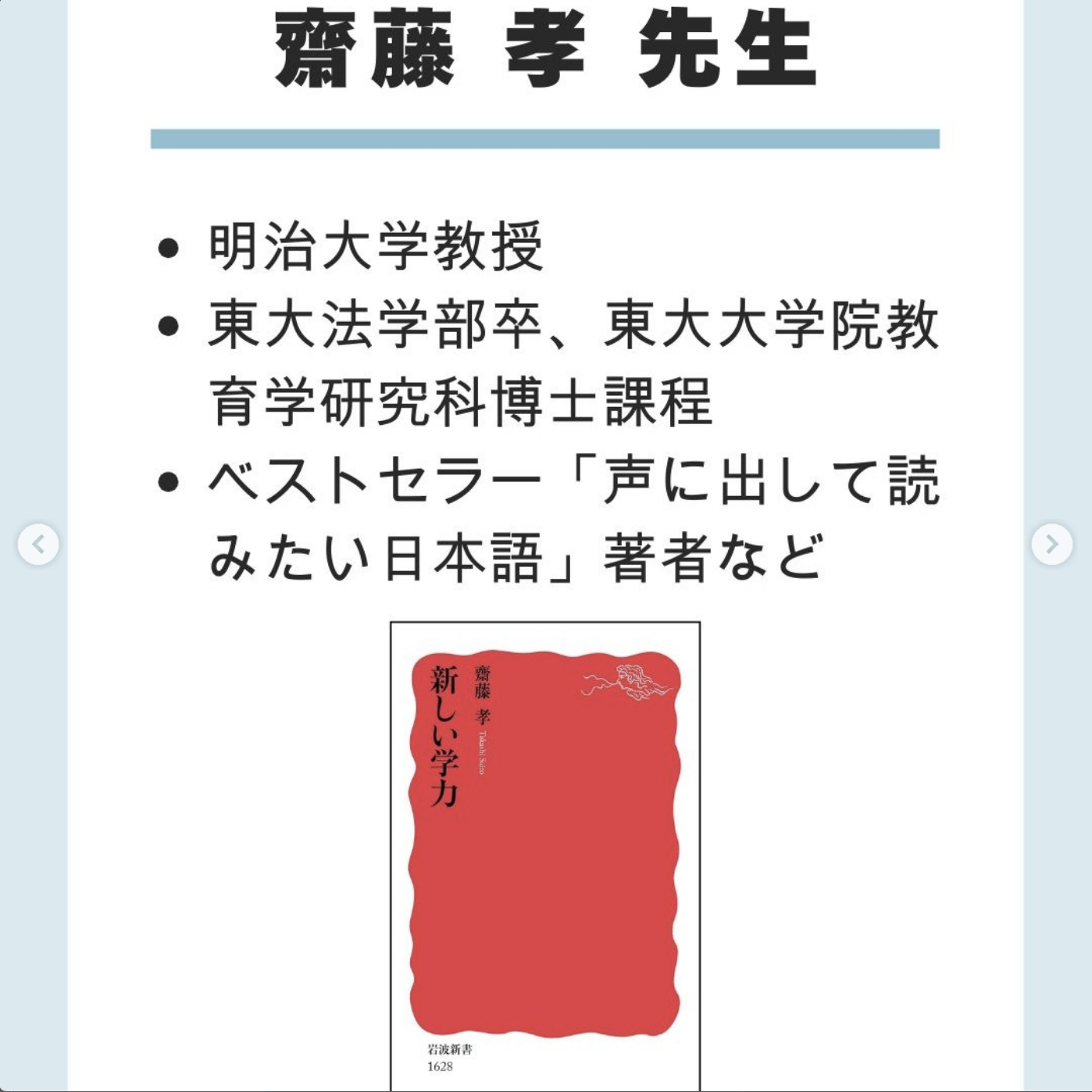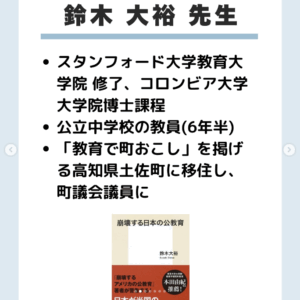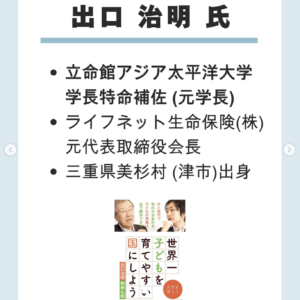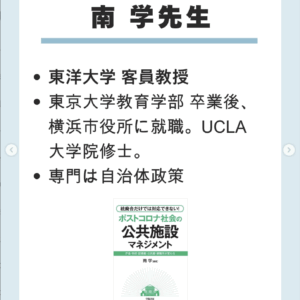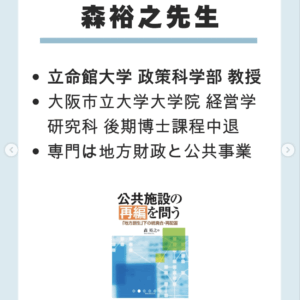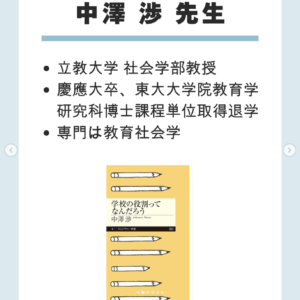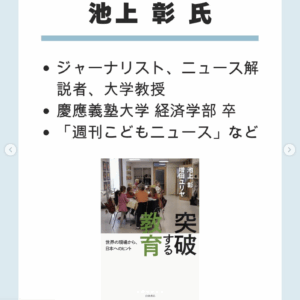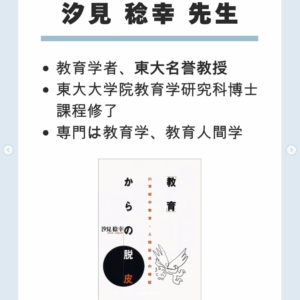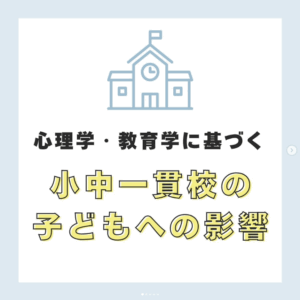学校再編計画の背景と目的
桑名市の「小中学校再編計画の背景」にはこう書かれています。
———–
現代は、急速に変化する時代+予測が困難時代
だから、「生きる力」の育成が必要。
具体的には、
- 自ら学ぶ力:主体性
- 課題を見つけ、考える力:問題解決力
- 対話と協働:人間関係形成力
(上記までは文科省の方針。下記からは桑名市の説明。)
そのためには、
多様な価値観に触れるために
【一定の集団規模を確保】することが大切??
だから、
【小中一貫の義務教育学校】が必要?????
生きる力の育成に必要なこと
「生きる力」の育成には
【集団規模の確保】と【義務教育学校】が
本当に必要なのでしょうか?
教育現場をよく知る齋藤先生の著書によれば、
「主体性」「問題解決力」「人間関係形成力」
いずれの育成においても、
【集団規模の確保】と【義務教育学校】
の必要性は見当たりません。
むしろ、「教え方(学びのスタイル)」が重要であり
「一人ひとり寄り添う丁寧なケア」が大事であると書かれています。
主体性
主体性=自分の関心・意欲に基づいて探求していく力
学ぶ意欲の源泉
1.「おもしろそう!」憧れる人の情熱/感動の伝播
2. 「できた!」習熟の喜び
問題解決力
問題解決力=自分で課題を見つけ、考え、解決する力
育成に必要なもの
1. 熟練のスキル
2.教育への情熱
3.一人ひとり寄り添う丁寧なケア
人間関係形成力
人間関係形成力=多様な他者の考えを理解し、自分の考えを伝え、協働して社会に参画していく力。
学びの方法
1. 課題・テーマの設定
2. 発表者による事前準備
3. 発表に対する肯定的なコメント
4. 少人数グループでの討議
5. 全員がそれぞれ発表
結局、桑名市の学校再編は、「生きる力」の育成とは関係ない
児童生徒数が1学年10人未満のような学校であれば、
「対話」と「協働」が制限されるため、
小学校同士、中学校同士の統廃合を行うことも合理的でしょう。
過疎化の進行した地域で、児童生徒数が極端に少ない状況であれば、
発達段階の大きく異なる小中学生であっても、一緒の学校にした方が良いかもしれません。
ですが、桑名の場合は状況が異なります!
「生きる力」の育成のためにすべきことは、
ハコモノ作りやマンモス校化ではなく、
教え方や体制など、ソフト面の改善ではないでしょうか?