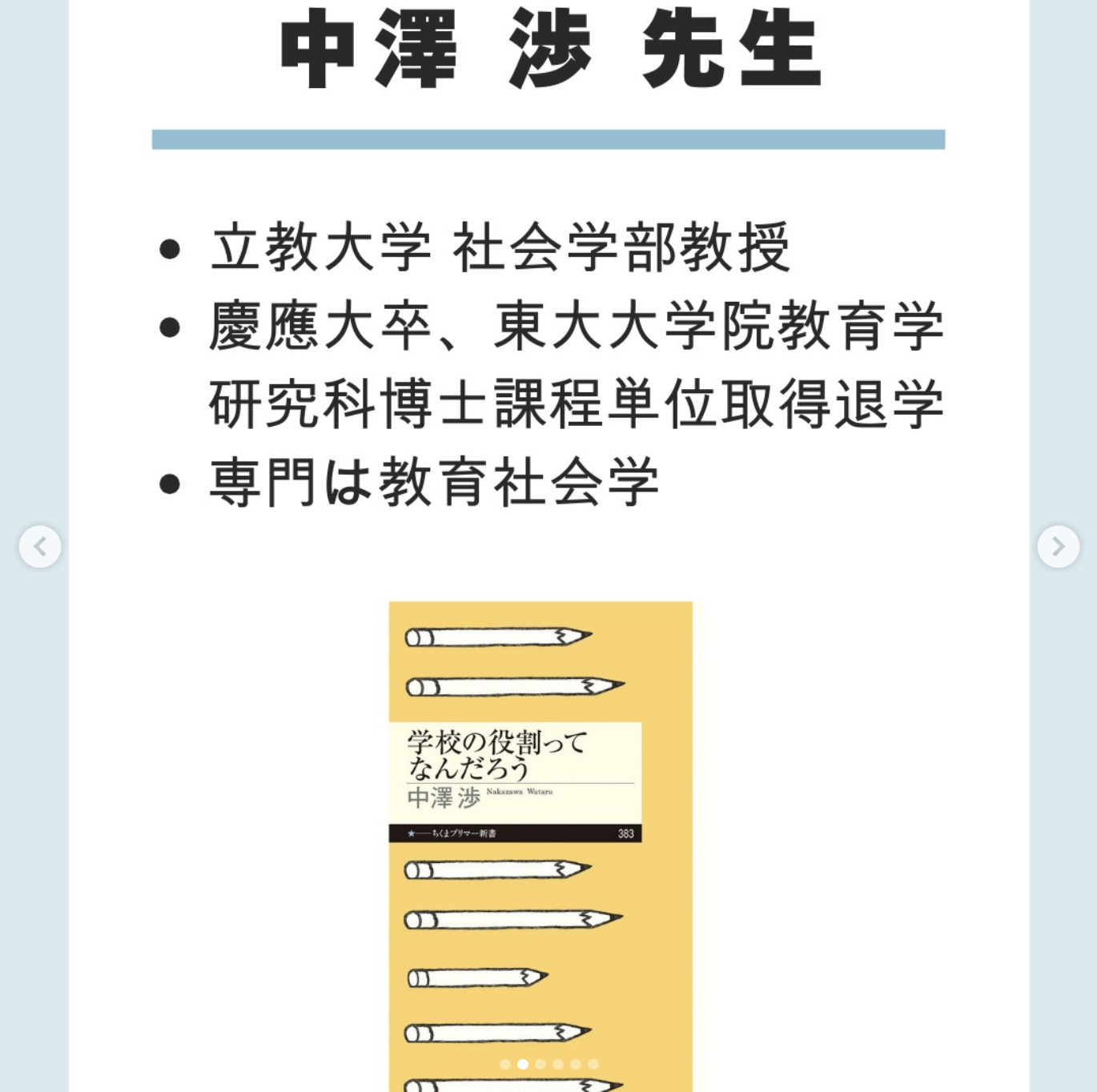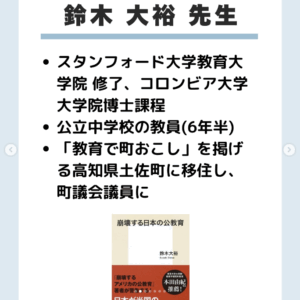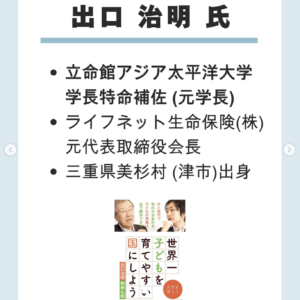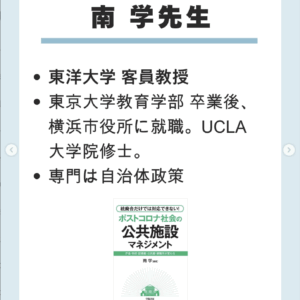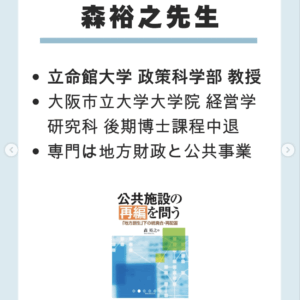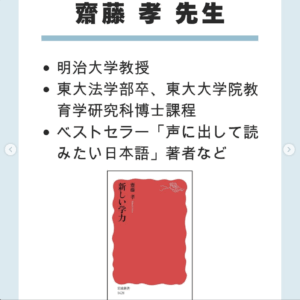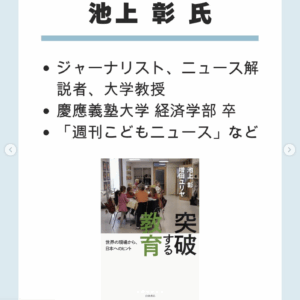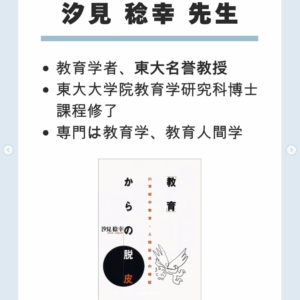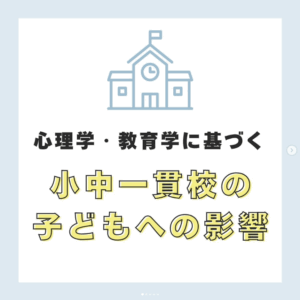小泉・安倍政権で急速に進んだ、政治による教育への介入。
「教え子を再び戦場に送るな」
そんな合言葉のもと、子どもと教育を守ってきた仕組み
世界から高く評価されてきた、日本式の教育の仕組みが、今危機に面しています。
そこで今回は、
これまで「学校が担ってきた役割とは何なのか?」
政権による教育改革の影響で、
学校の「塾化」が進んでいると言われる今、「学校と塾の違いとは何なのか?」
について、中澤先生の本から読み解きたいと思います。
学校の役割
①「学力」の向上
学力=読み書き、計算、科学、社会などの知識・学力(知育、教科指導)
・労働者の生産性UP
・個人の収入UP
・税収のUP
・社会の発展に寄与
→数字で測りやすい部分。教育支出=社会的投資。政権によって「特化」させられた部分。
ですが、学校の役割は「知育」だけではありません!
②人間性・社会性の向上
徳育・情操教育など=日直、係、給食当番、掃除、行事、クラブ、委員会などの「集団生活」で養う部分(生活指導)
・協働、助け合い、責任感、自己理解、他者の尊重UP
→数字で測れない、人間性の部分。政権によって「軽視」されてきた部分。
③社会的機能
・健康診断や予防接種などの公衆衛生
・防災訓練や交通安全教室
・地域コミュニティの中心
・地域の文化の拠点
・地域の防災の拠点
→②や③は、これまで海外から高く評価されてきた、日本の学校教育の強みです。
ですが、
「少子化」や「財源不足」、「効率化」の名の下に、こうした日本の学校教育の良さが、政治主導でどんどん削られてきています。
(※桑名市の学校統廃合計画も、同じ文脈で起きています。)
学校と塾の違い
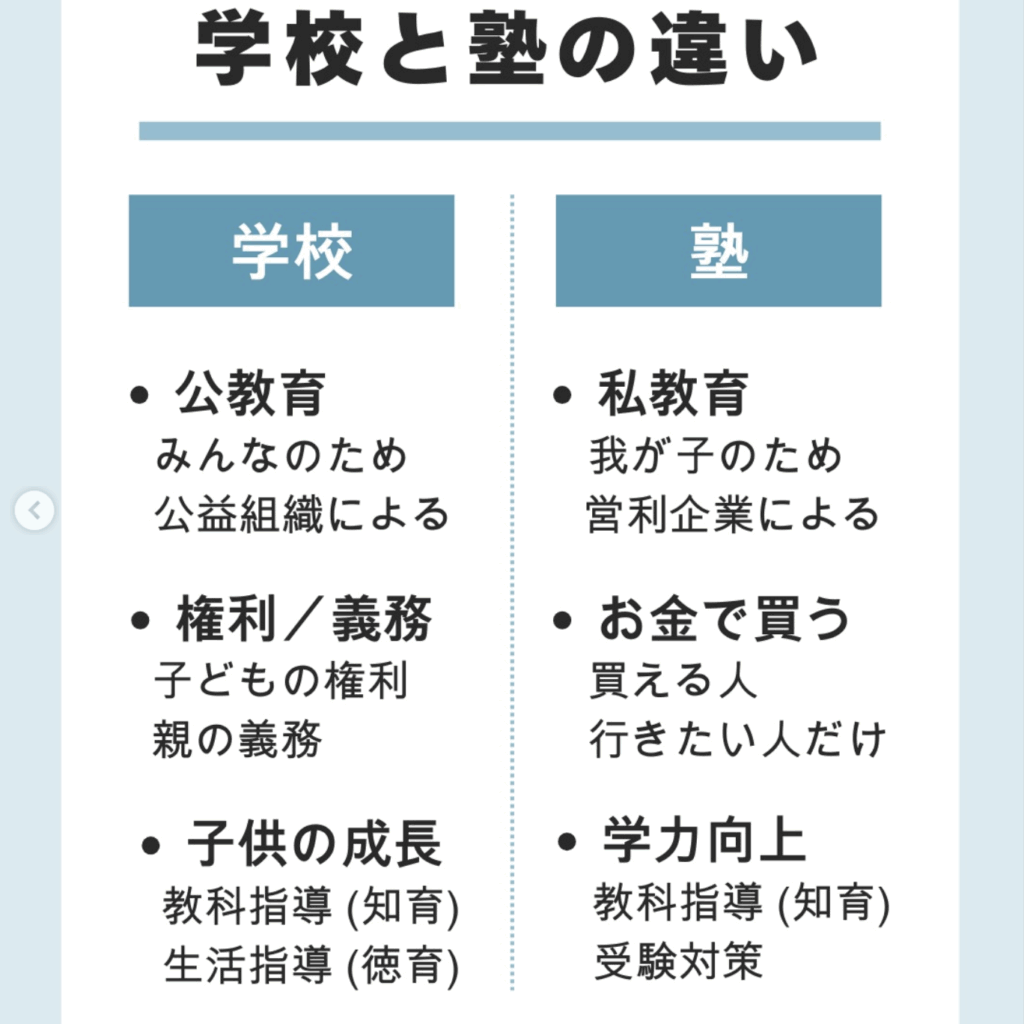
小学校、中学校段階の義務教育は、日本では「公教育」です。
出自や経済状況、学力や本人のやる気、性格に関わらず、
排除や差別をせずに行うのが「公教育」です。
どんな子どもでも「学ぶ権利」があり、親は通学させる「義務」があります。
そして、これまでの日本の学校では、
単に読み書き計算などの「学力」を伸ばすだけでなく
日直や給食当番、行事やクラブ活動などの集団生活を通じて
子どもの「人間的な成長」を育むことに、力が注がれてきました。
そして、こうした「子どもの全人的な成長」こそ、
学校の先生の専門領域でもありました。
それが・・・
時の政権による教育への介入で、
・「学力」偏重主義や競争主義
・学校の統廃合や正規雇用の教員削減
・教育の「商品」化や塾化
が起きているのが、日本の学校教育の現状です。