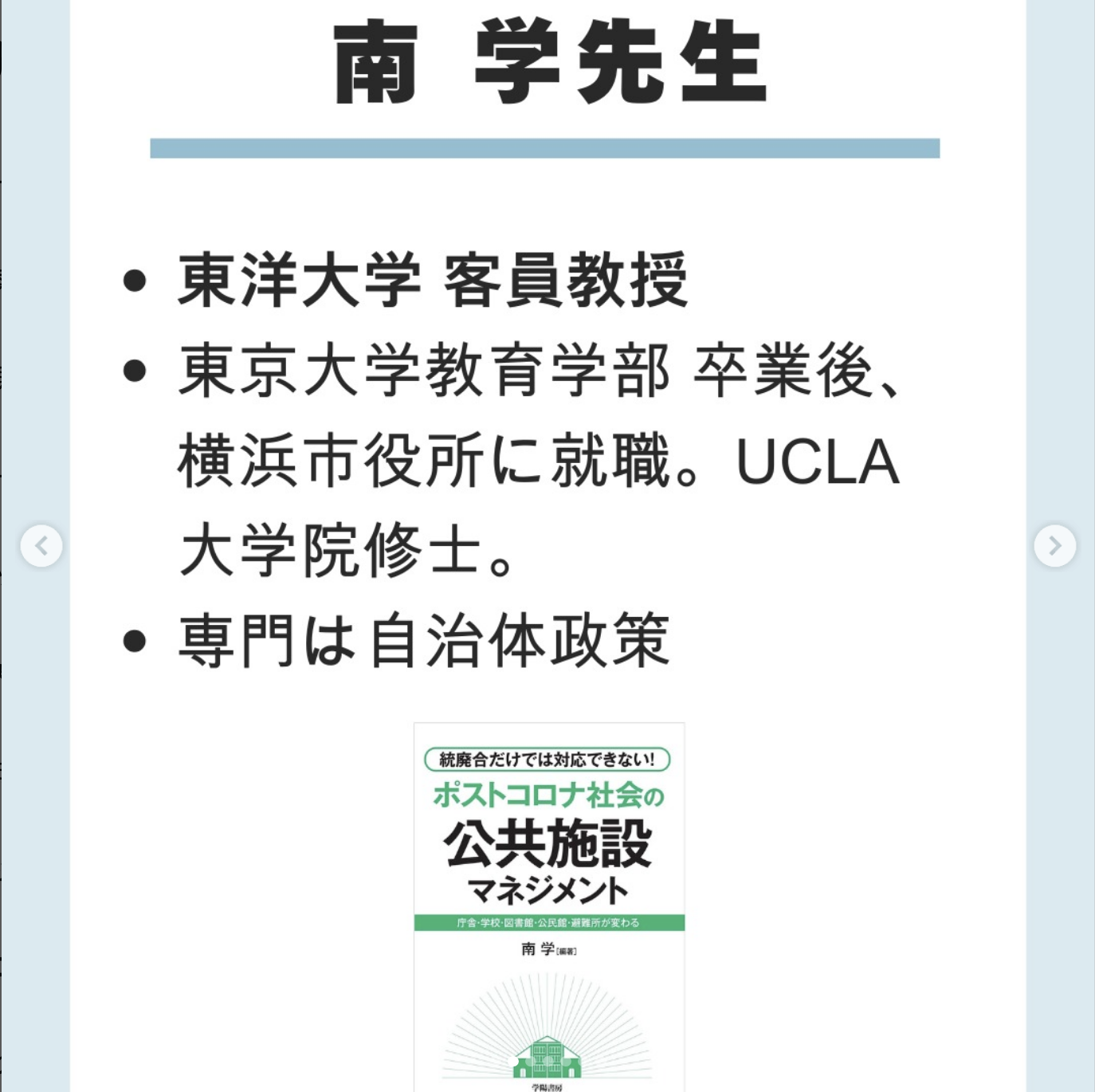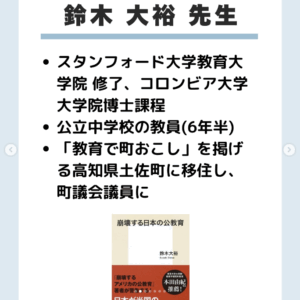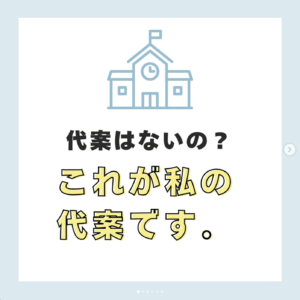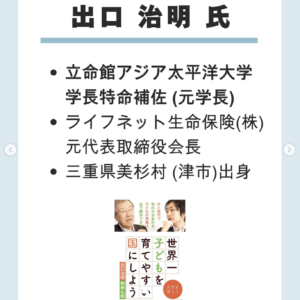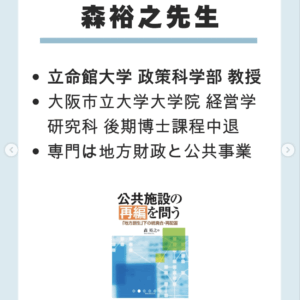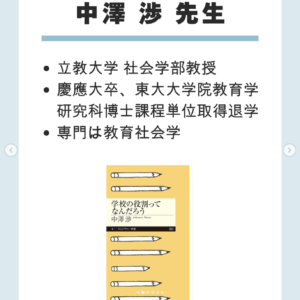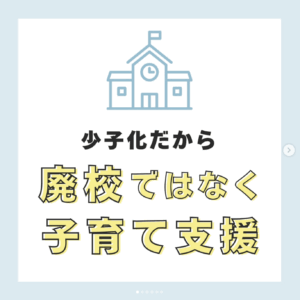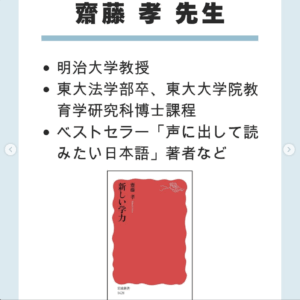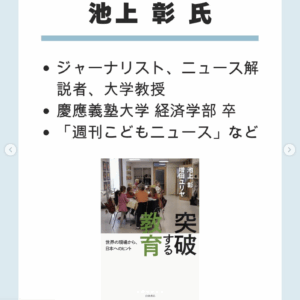総務省主催の首長・管理者向けセミナーで講師をされている先生の本です。
学校の統廃合を、公共施設の削減が至上命題となっている、行政側の立場や視点から、現実的な手法を説いています。
目次
学校の特徴
- 公共施設面積の約半分が学校
- 学校施設に児童がいない時間が半分以上
- 小学校は学区内から徒歩圏内にあり、広大な面積
- 近隣の公共施設と機能が一致している部分多い
学校を潰すのではなく、公共施設を学校に集約させる
1.学校の統廃合は行わない
(地域の分断や決裂につながり、実施が難しいため)
2.学校に他の公共施設の機能を集約させる [縮充]
(他の公共施設を減らす、学校設備の充実を図る、安全面や管理形態を整備する)
3.学校の将来的な転用も考慮した長寿命化計画を立てる
(教育委員会だけの事案にせず、企画、財務、他の部局との共同事案にする)
小学校を起点に地域が成り立ってきた歴史を無視して、
効率化の名の下に、地域から学校を奪い、
子どもたちにも遠距離通学や過剰な人間関係という負担を強いるより
今の学校を残し、多機能化・複合化させ、地域に解放する施策の方が、
よっぽど良いと感じたのは私だけでしょうか?
(もちろん安全面などは最大限対策する必要はありますが)
安全面の対策
- 放課後、土日祝日、長期休暇など、授業時間外に開放する
- 教員室やクラスルームなどの立ち入りを厳密に規制する
- 兵庫県明石市はほぼ全ての小中学校にコミュニティセンターを統合している
- 英国では学校が放課後、カルチャーセンターになり、学校の資金源にもなっている
運用面の対策
- 学校の地域開放は、法律でも積極的な規定
- 学校施設の管理責任、業務を校長から切り離す(教育委員会、市長部局)
- 現在の校庭/体育館開放は一部の団体のみが利用している状態
防災・避難拠点として
- 避難所の学校体育館が、難民キャンプの基準以下の雑魚寝状態という実態
- トイレ、更衣室・シャワー、断熱・空調などを整備する
- 災害対策だけでなく、学校の授業や地域のスポーツ活動などの利便性向上につながる