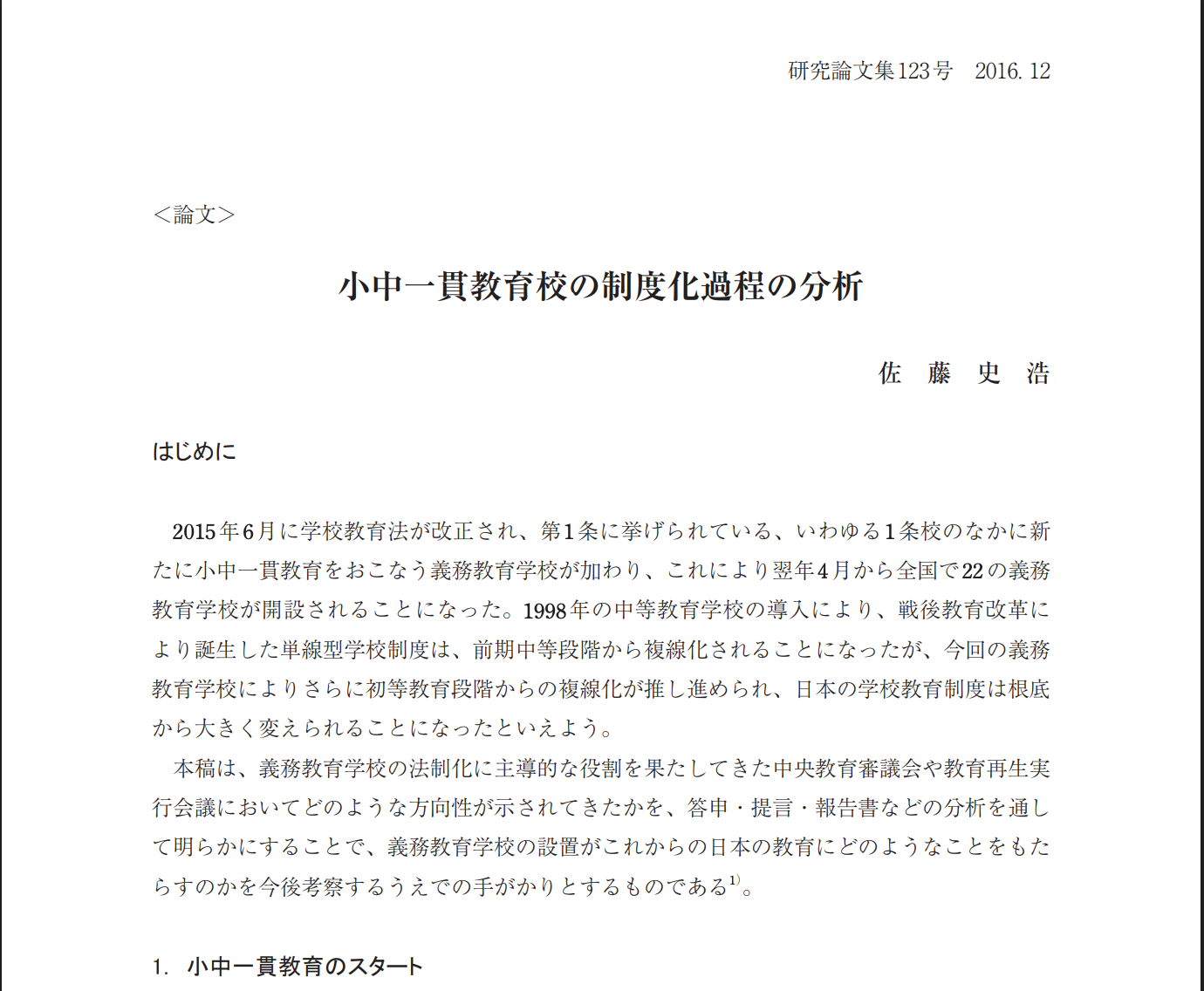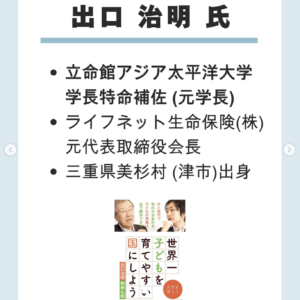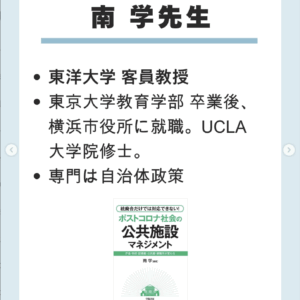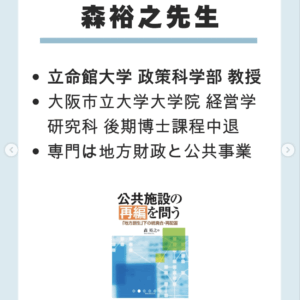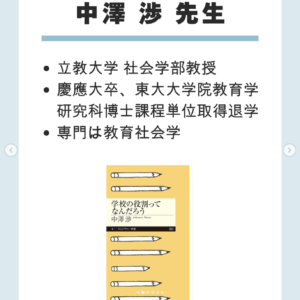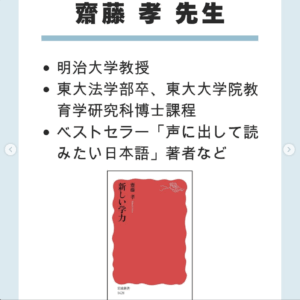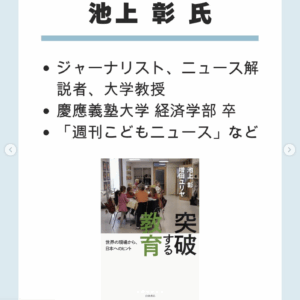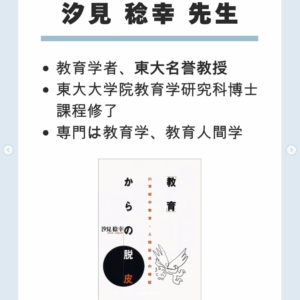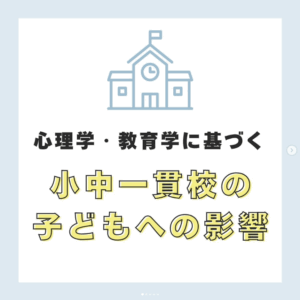小中一貫教育校の制度化過程の分析(佐藤 史浩 [宮城学院女子大学 教育学科教授]、2016)より抜粋します。
2000年、小中一貫教育のスタート
小中一貫教育を初めて導入したのは、広島県呉市である。2000年度に文部省研究開発学校の指定を受け、3小学校、1中学校を統合し、スタートしている。
一貫教育の導入のねらいは、義務教育9年間を修了するにふさわしい学力と社会性の育成と、中1ギャップの解消と自尊感情の向上とされた。
中1ギャップとは、いじめの認知件数、暴力行為の加害児童生徒数、さらに不登校児童生徒数が中学校1年生になったときに大幅に増えるなど、小学校から中学校への進学時に新しい環境での学習や生活に不適応を起こすことを総称するものである。
9年間は前期(4年)、中期(3年)、後期(2年)に区切られ、学習指導要領の範囲内で、各中学校区ごとに小中一貫カリキュラムが作成され、ことに中期に重点をおいた教育を展開するものとされ、この時期に一部の教科で教科担任制を導入することにした。
2012年、中教審作業部会 「小中連携、 一貫教育に関する主な意見等の整理」
<義務教育学校制度の創設に賛成との意見>
・地域の実情に応じた教育の実現のため、各学校や設置者の判断によって義務教育学校を設置できる仕組みは望ましい。
・義務教育を一体的に捉え9年間で児童生徒の学力向上を図っていく観点からは、義務教育学校制度の創設は極めて自然な発想であり、学習指導要領を満たしながら、9年間の学年区分(4・3・2や5・2・2など)については設置者が判断できるようにする。
・義務教育学校を創設し、教育課程を弾力的に編成できるようにする。
・小・中学校における教育課程上の無用な重複が省略できるのであれば、義務教育学校制度を創設する意義があるのではないか。
<義務教育学校制度の創設には慎重であるべきとの意見>
・義務教育学校では、9年間ほとんど同一の集団で学んでいくこととなり、児童生徒が9年間の途中で挫折した場合等、学校が変わることによる再チャレンジの機会がないこととなる。
・特に地方においては、学校が町の中心となっており、小・中学校が義務教育学校に一本化することで、学びの拠点である学校の数が減ることとなる。
・小中連携・一貫教育に取り組んでいる学校のねらいは、いわゆる中1ギャップの解消、学力向上、コミュニティの育成、小規模校の活性化等であり、義務教育学校制度の創設によりこうした課題が解決されるとは思えず、結論として制度の創設は時期尚早である。
・一部の学校に9年制を導入する場合、事実上学校制度の複線化となり、選択させるというが、小学校入学時の6歳の児童などでは通学できる範囲が限られ選択不可能であるうえ、一つの自治体の中に小学校、中学校、中等教育学校、義務教育学校があることがシステムとしてどのような効果をもたらすのかが不明である。
・義務教育学校では、人間関係が固定化し、新たに出発する機会が失われる等により閉塞感等を感じるものになる。
・義務教育段階で小・中学校と異なる義務教育学校を創設することにより、受験エリート校化、受験戦争の低年齢化を招くような事態が懸念される。
作業部会は(義務教育学校の)創設には慎重な検討を要するとしたうえで、義務教育学校制度の創設に期待されていることは、いずれも、現行制度において対応可能な面が多いとしている。
2014年、教育再生実行会議 「今後の学制等の在り方について」
中教審の作業部会が、現行制度のなかでの小中連携、一貫教育の推進を提言し、義務教育学校に関しては慎重な検討を求めていたのに対し、2年後の2014年7月3日に出された教育再生実行会議の第五次提言「今後の学制等の在り方について」は、対照的に義務教育学校の制度化を積極的に推進するものとなっている。
教育再生実行会議は、自由民主党の政権復帰、第二次安倍政権発足間もない2013年1月に設置された首相直属の会議で、第一次安倍政権下の教育再生会議で進められた教育改革のさらなる推進の役割を担うものであった。
第五次提言が小中一貫教育学校推進の理由としているのは、これを導入している多くの学校・自治体がその成果としてあげている中1ギャップの緩和、学力向上、さらには学習内容の高度化である。
しかし、小中一貫教育学校導入の大きなねらいは、グローバル人材養成のための学校制度の複線化であり、また学校統廃合を進めるうえでの手段である、といった以前から出されていた指摘に対し提言は答えていない。
小・中学校という複数の学校をまとめ、一部の学校を廃校にすることは、行政にとって人件費や施設費などのコストの削減をすることができる。この点が、小中一貫教育を短期間のうちに拡大させた最大の理由であると言われている。
全国に先駆けて小中一貫校を導入した呉市の場合、財政破綻を背景に学校維持費削減などのため、小中学校の統合の必要性が生じたといわれる。
また、品川区では学校選択制導入時に統廃合に結びつけないことを教育長が確約していたために、小規模化した学校を統合できずにいたといわれる。
教育再生実行会議の提言以後、中教審作業部会で提出された「義務教育学校制度の創設には慎重であるべきとの意見」はほとんど考慮されることなく、小中一貫教育学校制度化の方向へと進んでいくことになる。
国立教育政策研究所「『中1ギャップ』の真実」
中1ギャップへの対応は、当初から小中一貫教育導入の大きな理由として挙げられてきたものであるが、中央教育審議会が諮問を受けるちょうど数か月前、国立教育政策研究所より『「中1ギャップ」の真実』と題するリーフレットが発行されている。
これは、「中1ギャップ」という言葉に明確な定義はなく、その前提となっている事実認識も客観的事実とは言い切れないと、中1ギャップの存在を実体ととらえることに警鐘を鳴らすものであった。
たとえば、児童生徒を対象にした質問紙調査によれば、いじめの被害経験率は、小学校時代のほうが中学校時代よりも高く、中学校でいじめが急増するという印象は、あくまでも学校による「認知件数」の結果によるもので、それが実態を正確に反映しているかどうかは疑わしいとされている。
不登校についても、小6から中1への増加率は、「問題行動等調査」によれば、3倍とされているが、小学校時の欠席理由をもとに数え直したところ、1.3倍前後で、必ずしも急増とは言えないとされている。
また、中学進学に対する小学生の不安感が不登校を急増させる話については、・・・不安感が不登校の直接的な原因とはいえないことが示されている。
2015年、義務教育学校スタート
2015年6月に学校教育法が改正され、第1条に挙げられている、いわゆる1条校のなかに新たに小中一貫教育をおこなう義務教育学校(施設一体型の小中一貫校)が加わり、これにより翌年4月から全国で22の義務教育学校が開設されることになった。
まとめ
このように制度化された背景を紐解くと
・教育現場や専門家からは、義務教育学校に対して慎重論が多かった
・当時の政権の方針により、政治主導で突然慎重論が黙殺され、制度化が推進された
・学校維持費(コスト)削減目的で、学校の統廃合と義務教育学校の創設が急速に広まった
といった隠された歴史が読み取れます。
桑名市による「全市一律の義務教育学校化」計画も、子どもたちのためではなく、数字しか見ていない、現場を知らない人たちによる、コスト削減のための強引な計画である、と感じるのは私たちだけでしょうか?